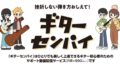※本ページはプロモーションが含まれています。
「ギターメンテナンスの頻度って、実際どのくらいがベストなの?」と、疑問に思ったことはありませんか。エレキギターやアコギのメンテナンスを自分で行う場合、ギターのワックスの頻度はどのくらいか、ギターの弦が錆びるまでの期間はどの程度か、といった具体的なお手入れのタイミングは分かりにくいものです。
また、長年ケースにしまい込んでいた放置ギターのメンテナンスや、弾き心地に直結するネック調整の頻度についても気になるところでしょう。一方で、プロの店にメンテナンスを依頼する際の料金も知っておきたいですし、状態が良くないギターを持ち込むのはギターリペアが恥ずかしいと感じてしまう方もいるかもしれません。この記事では、そんなギターメンテナンスの頻度に関するあらゆる疑問に、お答えしていきます。
|
この記事のポイント
|
基本的なギターメンテナンス頻度と自分でできること
|
メンテナンスを自分でするメリットと注意点
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
ギターのメンテナンスを自分で行うことには、多くのメリットがあります。最も大きな利点は、コストを抑えられることと、自分の楽器への理解が深まることでしょう。弦交換やクリーニングなど、基本的なメンテナンスを自分で行う習慣をつけることで、楽器店に支払う工賃を節約できます。また、日常的に楽器に触れることで、ネックのわずかな反りやパーツの緩みといった小さな変化に気づきやすくなるのです。これが、大きなトラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
自分でメンテナンスするメリット
- メンテナンスにかかる費用を節約できる
- 自分のギターの構造や状態を深く理解できる
- 楽器への愛着がさらに増す
- 細かなコンディションの変化に気づき、トラブルを早期発見できる
一方、自分でのメンテナンスには注意点も存在します。専門的な知識がないまま作業を行うと、かえって楽器の状態を悪化させてしまうリスクがあるのです。特に、ネックの反りを調整するトラスロッドの操作や、弦高調整などは非常にデリケートな作業です。力を入れすぎたり、間違った方法で調整したりすると、修理が困難なダメージを与えてしまう可能性もあります。
自分でメンテナンスする際の注意点
十分な知識を持たずにデリケートな調整を行うのは避けましょう。ネック調整や電気系統の修理など、自信がない作業は無理せずプロに依頼するのが賢明です。また、作業にはニッパーやドライバー、専用のオイルやクロスなど、適切な工具や用品を揃える必要があります。
放置したギターのメンテナンスは必要?
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
結論から言うと、長期間弾かずに放置していたギターは、演奏を再開する前に必ずメンテナンスが必要です。ギターは主に木材でできているため、弾いていなくても保管環境の温度や湿度の影響を受け続けています。特に日本の気候は季節による温湿度変化が激しいため、数ヶ月から1年放置しただけでも、コンディションは大きく変わっている可能性があります。
放置によって起こりやすいトラブル
長期間の放置で最も懸念されるのがネックの反りです。弦の張力にネックが負けて順反りになったり、逆に逆反りになったりすると、弦高が極端に高くなったり、特定のフレットで音が詰まる「ビビり」が発生したりします。
また、弦は空気に触れているだけで酸化し錆びてしまうため、音質が劣化し、チューニングも不安定になります。その他にも、金属パーツのくすみや錆、ボディや指板の乾燥によるひび割れ、埃の蓄積による電気系統の接触不良など、様々なトラブルが考えられます。
「昔買ったギターを久しぶりに弾いてみようかな」と思ったら、まずは楽器の状態をしっかりチェックすることから始めましょう。見た目が綺麗でも、弾きやすい状態とは限りません。まずは新しい弦に交換し、その際に指板やボディのクリーニングを行うのがおすすめです。
ギターの弦が錆びるまでの期間と交換目安
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
ギターの弦が錆びるまでの期間は、演奏頻度や保管環境、さらにはプレイヤーの手汗のかきやすさによって大きく異なります。一概に「何日で錆びる」とは言えませんが、交換のタイミングを見極めるサインを知っておくことが重要です。
弦交換の一般的な目安は1ヶ月から3ヶ月に1回と言われています。しかし、これはあくまで目安です。毎日何時間も弾く方であれば2週間に1回の交換が必要な場合もありますし、逆にほとんど弾かない方でも、空気中の湿気によって自然と劣化は進みます。
交換時期を判断するには、以下のサインに注目しましょう。
- 見た目:弦が黒ずんでいたり、茶色い錆が浮いていたり、光沢がなくなってくすんでいる。
- 手触り:指で触った時にザラザラとした感触がある。チョーキング(弦を押し上げる奏法)がしにくい。
- 音質:新品の時のような「シャリーン」とした煌びやかな高音がなくなり、音がこもって聞こえる。サスティン(音の伸び)が短くなる。
- チューニング:チューニングをしても、すぐに音が狂ってしまう。オクターブピッチが合わない。
…
これらのサインが1つでも当てはまれば、それは弦の交換時期です。古い弦を使い続けると、良い音が出ないだけでなく、フレットを無駄に摩耗させてしまう原因にもなります。
| 演奏頻度 | 交換時期の目安 |
|---|---|
| 毎日(2時間以上) | 2週間~1ヶ月 |
| 週に2~3回 | 1ヶ月~2ヶ月 |
| 月に数回 | 3ヶ月 |
| ほとんど弾かない | 半年に1回(演奏しなくても交換を推奨) |
ギターのワックスの頻度はどのくらいが最適?
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
ギター用のワックス(一般的にはポリッシュと呼ばれます)は、毎回の演奏後に使用する必要はありません。最適な使用頻度は、弦交換のタイミングと重なる数ヶ月に1回程度、もしくはボディの指紋や汚れが目立ってきたときで十分です。
ポリッシュの主な役割は、塗装面の汚れを落とし、美しい艶を出し、静電気を防いでホコリの付着を抑えることです。しかし、研磨剤が含まれている製品もあり、頻繁に使用すると塗装面にダメージを与えてしまう可能性があります。日常的なお手入れは、演奏後に乾いた柔らかいクロス(マイクロファイバークロスなど)で全体を優しく拭くだけで問題ありません。
ポリッシュ使用時の重要注意点
ギターの塗装には様々な種類があり、中にはポリッシュの使用が適さないものもあります。特に「ラッカー塗装」や「オイルフィニッシュ」といったデリケートな塗装のギターに、対応していないポリッシュを使うと、塗装を溶かしたり変質させたりする危険性があります。
使用前には必ずポリッシュの注意書きを確認し、自分のギターの塗装に対応しているか確かめましょう。また、ポリッシュはボディ用です。塗装されていない指板(ローズウッドなど)や、金属パーツには使用しないでください。
エレキギターで特に注意すべきメンテナンス
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
エレキギターのメンテナンスでは、アコースティックギターにはない電気系統のチェックが非常に重要になります。これらは演奏の要であり、トラブルが起きると音が出なくなってしまうこともあります。
ジャックの緩みとガリ
シールドケーブルを差し込むジャック部分は、抜き差しを繰り返すうちにナットが緩みやすい箇所です。緩んだまま使用を続けると、内部で配線がねじれて断線する原因になります。定期的に緩みがないかチェックし、手で締めるか、ボディ内部の配線を傷つけないように注意しながらレンチで軽く締めましょう。また、ケーブルを動かした際に「ガリガリ」というノイズが出る場合は、ジャック内部の接触不良や汚れが考えられます。接点洗浄剤で改善することもありますが、頻発するなら交換が必要です。
ポットやスイッチのチェック
ボリュームやトーンのノブ(ポット)を回した時や、ピックアップセレクタースイッチを切り替えた時にノイズが出る場合も、内部の劣化やホコリが原因です。これらも消耗品のため、症状が悪化すれば交換を検討しましょう。
オクターブチューニング
エレキギターはブリッジのサドルを個別に調整できるため、より正確な音程を得るためのオクターブチューニングが可能です。弦交換をした際や、弦のゲージ(太さ)を変えた際には、チューナーを使って開放弦と12フレットの音が正確に1オクターブ違いになるよう調整することをおすすめします。
アコギならではの調整とメンテナンス
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
アコースティックギターのメンテナンスで最も注意すべき点は、湿度管理です。ボディ全体が空洞で、使われている木材も薄いため、周囲の湿度の影響を非常に受けやすい構造になっています。
最適な湿度と管理方法
ギターにとっての最適な湿度は、一般的に45%~55%と言われています。これより湿度が低い「過乾燥」の状態が続くと、ボディトップ材の木材が収縮して割れてしまったり、指板が縮んでフレットの端が飛び出す「フレットバリ」の原因になります。逆に湿度が高すぎる「多湿」の状態では、木材が水分を吸って膨張し、音がこもったり、ブリッジが剥がれてしまったりするリスクが高まります。
湿度管理の具体策
- 湿度調整剤の使用:ハードケースに入れて保管し、ケース内にギター用の湿度調整剤を入れるのが最も効果的です。
- 冬場の乾燥対策:暖房で空気が乾燥しがちな冬場は、加湿器を使用したり、ケース内に保湿剤を入れたりするなどの対策が有効です。
- 梅雨の多湿対策:ケース内の湿度調整剤を新しいものに交換したり、部屋で除湿器を稼働させたりしましょう。
サドルによる弦高調整
アコギの弦高は、主にブリッジにはまっているサドルというパーツの底面を削ることで調整します。弦高が高くて弾きにくいと感じる場合は、サドルを削って低くすることが可能です。ただし、一度削ると元には戻せないため、少しずつ慎重に作業するか、プロに依頼するのが安全です。逆に弦高が低すぎてビビる場合は、新しいサドルに交換する必要があります。
プロに頼むギターメンテナンス頻度とお店選び
|
ネック調整の頻度とプロに任せる基準
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
ギターの弾き心地を左右する最も重要な要素が、ネックのコンディションです。ネック調整の頻度は、年に1~2回、特に季節の変わり目である梅雨時期と冬の乾燥時期にチェックするのが理想的です。
ネックの反りは、レンチを使ってネック内部のトラスロッドという金属の棒を回すことで調整します。わずかな調整であれば自分で行うことも可能ですが、これは非常にデリケートな作業です。どのくらい回せば良いか分からなかったり、回すのが固いと感じたりした場合は、無理をせずにプロに任せるのが賢明です。
プロにネック調整を任せるべき基準
- 自分でトラスロッドを回すのが怖い、自信がない
- レンチを回した際に、少しでも固いと感じた
- 順反りや逆反りだけでなく、ネックがねじれているように見える
- 調整しても弦のビビりや音詰まりが改善しない
- そもそも調整方法が分からない
特に、トラスロッドを回すのに強い力が必要な場合は、すでに限界まで締まっているか、固着している可能性があります。無理に回すとロッドが折れてしまい、修理に高額な費用がかかるため、すぐに専門のリペアショップに相談してください。
安心して任せられる店の選び方
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
大切なギターのメンテナンスを任せる店を選ぶ際は、料金の安さだけでなく、技術力と信頼性で判断することが重要です。良いリペアショップや楽器店を見つけることが、ギターを長く良い状態で使い続けるための鍵となります。
信頼できる店のチェックポイント
- カウンセリングの丁寧さ:楽器の状態をチェックするだけでなく、「どんな音楽を弾くのか」「どんな弾き心地が好みか」といったプレイヤーの要望を丁寧にヒアリングしてくれるお店は信頼できます。
- 修理内容と料金の事前説明:作業を始める前に、どのような修理が必要で、費用がいくらかかるのかを明確に説明してくれることが大切です。不明瞭なまま作業を進めるような店は避けましょう。
- 実績と評判:お店のウェブサイトやSNSで修理実績を確認したり、口コミを参考にしたりするのも良い方法です。長く営業しているお店や、プロのミュージシャンからの信頼が厚いお店は、高い技術力を持っていることが多いです。
どこに頼めば良いか分からない場合は、まずそのギターを購入した楽器店に相談してみるのがおすすめです。購入店であれば、そのギターの特性を理解している可能性が高いですし、提携している信頼できるリペア工房を紹介してくれることもあります。
ギターリペアが恥ずかしいと感じる必要はない
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
「自分でいじって壊してしまった」「ボロボロすぎて見せるのが恥ずかしい」「安いギターだから頼むのが申し訳ない」といった理由で、リペアショップに楽器を持ち込むのをためらってしまう方がいらっしゃいます。しかし、そのような心配は一切不要です。
プロのリペアマンは、日々様々な状態の楽器を見ています。新品同様のギターから、何十年も使い込まれたヴィンテージギター、初心者向けのモデルまで、あらゆる楽器の修理や調整が彼らの仕事です。むしろ、楽器を良い状態で長く使おうという気持ちで相談に来てくれることを歓迎してくれます。
リペアマンは、いわば「楽器のお医者さん」です。どんな些細な悩みでも、親身に相談に乗ってくれます。「こんなことを聞いたら笑われるかも」などと思わず、気になっていることは全て伝えてみましょう。それが、あなたのギターを最適な状態にするための第一歩です。
自分で挑戦した結果うまくいかなかったとしても、正直にその経緯を伝えることで、リペアマンは原因を特定しやすくなり、よりスムーズな修理に繋がります。恥ずかしがらずに、気軽に相談してみてください。
メンテナンスを店に頼む際の料金の目安
 ギターナビ・イメージ
ギターナビ・イメージ
楽器店やリペアショップにメンテナンスを依頼する際の料金は、作業内容によって大きく異なります。簡単な調整であれば数千円で済みますが、パーツ交換や大掛かりな修理になると数万円以上かかることもあります。以下に一般的な料金の目安をまとめましたが、これはあくまで参考です。正式な料金は、必ずお店に見積もりを依頼して確認してください。
| メンテナンス項目 | 料金の目安(パーツ代別途) | 備考 |
|---|---|---|
| 弦交換 | ¥500 ~ ¥1,500 | 弦代は別途必要。ロック式など特殊なブリッジは高くなる傾向。 |
| ネック調整 | ¥1,000 ~ ¥5,000 | 弦高やオクターブ調整を含む全体調整セットになっていることが多い。 |
| フレットすり合わせ | ¥6,000 ~ | フレットの一部が消耗した場合に、全体の高さを揃える作業。 |
| ナット交換 | ¥3,000 ~ | 素材(牛骨、TUSQなど)によってパーツ代が変わる。 |
| ピックアップ交換(1基) | ¥3,000 ~ ¥5,000 | 配線の加工が必要な場合は追加料金がかかることがある。 |
| ジャック交換 | ¥1,000 ~ | 比較的安価で対応可能な修理の代表例。 |
| ネック折れ修理 | ¥35,000 ~ | 折れ方や塗装の再現度によって料金が大きく変動する。 |
多くのショップでは、ネック調整、弦高調整、オクターブ調整などをセットにした「全体調整」といったメニューを用意しています。定期的なメンテナンスであれば、このようなセットメニューを利用するのがお得で効率的です。
最適なギターメンテナンス頻度で愛器を守ろう
この記事では、ギターメンテナンスの頻度について、ご自身で行う場合とプロに依頼する場合の両面から解説してきました。最後に、大切なポイントをまとめます。
- ギターメンテナンスの基本は日々のクリーニングから始まる
- 自分でメンテナンスをするとコストを抑えられ楽器への理解が深まる
- 自信のない調整や修理は無理せずプロに依頼するのが賢明
- 長期間放置したギターは演奏前に必ずメンテナンスが必要
- 弦交換の目安は1ヶ月から3ヶ月だが錆や音の変化が見られたら交換
- ギターワックス(ポリッシュ)の使用は数ヶ月に1回程度で十分
- エレキギターはジャックやスイッチなど電気系統のチェックが重要
- アコギは湿度管理が最も大切で最適な湿度は45%から55%
- ネック調整のチェックは季節の変わり目ごとに行うのが理想
- トラスロッドを回すのが固いなど異常を感じたらすぐにプロに相談
- リペアショップは料金だけでなくカウンセリングの丁寧さや実績で選ぶ
- どんな状態のギターでもリペアに出すことを恥ずかしいと思う必要はない
- メンテナンス料金は作業内容で大きく異なるため必ず事前見積もりを取る
- 定期的なメンテナンスがギターを良い状態で長く保つ秘訣
- 何よりも一番のメンテナンスは毎日ギターを弾いてあげること